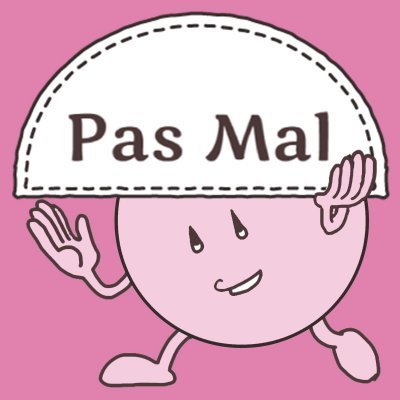モラハラを受けて離婚した元夫と、2か月に1回の頻度で面会交流をしている我が家の息子。
離婚から約5年がたち、我が家の面会交流は変化の時期を迎えています。
我が家の面会交流の今について詳しくご紹介していきます。
このお話は音声でも聞いていただけます。手軽に音声で聞いてみてくださいね。
シングルマザーのまるはスタンドエフエムという音声アプリで毎日配信をしています。
良かったら聞きに来てみてください。
目次
我が家の面会交流についてのあらまし

数年にわたって、第三者機関の協力のもと面会交流を続けてきた息子と元配偶者。
第三者機関について気になる方はこちらをご覧ください。
FPic(エフピック)という第三者機関からの支援を受けている我が家。
支援とは具体的に、面会交流について、日時決めの連絡を代行してくれるところから面会時間丸ごと息子に付き添ってくれる「付き添い型」の支援や、日時決めの連絡を代行してくれ、面会当日は養育親との待ち合わせ場所から面会親との待ち合わせ場所までの送迎をしてくれる(歩いて5分程度)「受け渡し型」など、いくつかの種類があります。
我が家は、面会交流開始当初から2年程度は付き添い型、それ以降現在までは受け渡し型で支援を受けてきました。
モラハラが離婚の原因で、更に調停を3つしてすっかり元配偶者恐怖症になってしまった私には、離婚当時直接面会の連絡をすることが難しく、裁判所の判断で第三者機関を利用して面会をすることになったというわけなんです。
そうして数年にわたって利用させてもたった第三者機関を今、卒業することを考えているんです。
第三者機関を卒業することを考えていた私

そもそも、第三者機関は永遠に使えるものではありません。
子供が大きくなって、自分で連絡ができるようになったり、元夫婦が自分たちで連絡調整をできるようになれば卒業すればいいですし、そもそも子供が4年生になるまで(もしくは4年生のうちまで)という大まかなリミットも設けられていますので、いずれは卒業しなくてはならないんです。
我が家の場合は、あと1年利用させてもらうこともできるタイミングではありましたが、息子も大きくなってきて、そろそろ卒業を意識していたわけなんです。
元夫に直接連絡を取りあることを打診した
そこで私は、第三者機関の担当者さんを通じて、その考えを元夫にぶつけてみることにしました。
第三者機関を通じて、面会のあり方を改めて見直すよう促した

ただ、私には心配事がありました。
それは、ここのところの元夫の態度。
面会の日程をドタキャンしてきたり、第三者機関の規約に違反することをしたり。そういうことがあると、第三者機関を卒業したらもっと傍若無人になっていくだろうと予想できますよね。
それが怖かったんです。
そこで、第三者機関の方の存在があるうちに一度しっかりと釘を刺しておこうと思ったわけです。
一度決めた日程を仕事の都合で直前に変更しようとしないことや、誕生日とクリスマス以外のプレゼントは禁止など、元々の取り決めを再度念押ししてもらうことにしました。
更に、先日それらの決めごとを元夫が破ったことについて、それが元で息子にどのような影響があったか、我が家がどのように荒れたのかを克明に話して、二度としないように強く伝えてもらうようにしました。
息子のADHDを初めて明言した
それにあたって、なぜそのようにこちらが決まりごとに拘るのか?を明らかにするため、初めて息子のADHDについて元夫に伝えることにしました。
軽度のADHDであること、自閉症の合併はないこと。
多動や衝動性を抑えるのが難しい傾向にあること。
年々落ち着いて、息子なりの成長があること。
しかし、面会時に元夫の協力が得られなければ、前回のような問題が起きてしまうことなどを詳しく話しました。
第三者機関の方には発達障害があるということは伝えていましたので、すんなりと話を聞いてもらえました。
元夫の返答は「第三者機関契約継続」だった
ところが、問題はここから。
第三者機関の方から話を聞いた元夫は、以下のような質問をしてきました。
ADHDとは、正式な診断を受けての発言か。
元嫁(私)が勝手に言っているだけなのではないか。
これはまあ、想定内。
元夫は離婚のときから自分に落ち度があってもすべて私のせいと言い放つことが多かったので、こんな感じのことは言われるだろうと思っていました。
ADHDとは正直動揺している。
直接息子と連絡を取り合うのはまだできそうにない。
もう一年、第三者機関の支援を受けたい。
ナニコレ?
できそうにないって何?
まあ、発達障害をいきなり突き付けられたら動揺もするのでしょうね。
育て親ではないから心の準備ができていないことは仕方がないことなのかもしれません。
ただ、これまで面会を重ねてきたのだから、息子の多動性や衝動性には少なからず気づいているだろうと思っていた私の予想は全く覆されることになったのでした。
仕方がないという気持ちと、「お前は子供の何を見ているんだ」という気持ちと、正直半分半分。
複雑だけれど、相手がまだ直接やり取りできると思えるようにならないならば、今第三者機関を卒業するのは難しいという結論に達しました。
あと1年第三者機関にお世話になって面会をすることになった

そんなこんなであと1年は第三者機関に「連絡調整型」といって、当日現地には来ないけれど、事前の連絡取りだけはしてもらうという方法で援助を継続してもらうことになった我が家。
援助を受けるということは費用が掛かるということなので、そこはちょっとネックですが、正直に言えば私も自分で元夫と連絡を取りたいとは全く思っていないので、ちょっと安心したのも事実なんです。
1年後には息子に連絡を取ってもらえるように練習してもらおう。
私もその頃には心境の変化があるかもしれないし。
無理無理と考えるのではなくて、そのうち何とかなるかも!くらいに考えて楽にあと1年を過ごしてみたいと思います。
我が家と同じく面会交流に問題を抱えている方の参考になればと思って、今後も記事を書いていきます。
何かご質問があればどうぞお気軽にご連絡ください。