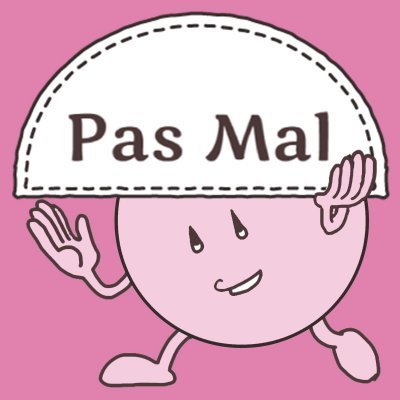ネットショップPas Malを運営している私、まる。
今回、嬉しいことにネットショップを飛び出して、実際のお店の一角にPas Malの商品を置かせていただけることになりました!
ネットショップと実店舗での必要な物の違いなどをまとめます。
目次
ネットショップだけで販売していたけれど、実店舗にデビュー!

ネットショップをオープンしてから、有難いことに商品をご購入くださる方に恵まれて、楽しく運営してきました。
そんな中で頂いた、実店舗への商品陳列。
こんなにありがたい申し出はありませんので、二つ返事で「やらせてください!!」と言いました。
飛んで喜んだけれど、次の瞬間気づく「準備不足」
でも、喜びもつかの間、気づきました。
お店の社長さんとの顔合わせまでの時間は1週間。
普段、マイペースにネットショップを運営していた私には、足りないものが多すぎる!
急遽、ブログやYoutubeなど、普段している副業をすべてストップしてショップ準備に取り掛かることになりました。
お話をもらってから実際に商品を置くまでの流れ
ハンドメイドアクセサリーに限らず、個人で商材を制作している人が実店舗にその商品を置かせてもらうための流れを大まかに紹介するとこんな感じです。
実店舗に商品を置くお話が出る
↓
商談用の商品を準備する
↓
商談する
↓
商材が決まる
↓
店頭にディスプレイさせてもらう
↓
陳列情報などをまとめた表を共有する
そもそも陳列してもらう商品数を満たすほど手元に作り溜めていなかったので大慌て!
夜な夜な準備にいそしむ1週間が始まりました。
ネットショップを運営するために必要なモノ

ネットショップて、思っているよりずっと簡単にオープンできるんですよ。
備品面で見て必要なモノを見てみましょう。
商品を撮影するためのカメラ
まず、自分で商品画像を撮影する場合にはカメラが必要です。
とはいっても、本格的なカメラを購入する必要はなし。
今のスマートフォンの性能はカメラ顔負けなので、スマートフォンで十分に代用が可能です。
むしろスマホでそのまま色彩補正ができたりして、すごい時代になったものですね~。
商品を撮影するための備品
写真を撮るのに、商品を美しく見せたり、写真そのものの見栄えを考えると撮影場所や備品は大切な要素。
商品を置く台を木目の美しいテーブルやチェストにするとか、もしくは大理石調のプレートにするとか、好みとショップコンセプトによって適した備品を用意する必要があります。
どうしてもしなくてはならないということではありませんが、直接商品の魅力を伝えることのできないネットショップにとって、写真を美しく見せることはとっても大切なことです。
ほんの少しのWEBの知識
今って、ネットショップを作るのに特別な知識は必要ありません。
現在、Pas MalはBASEでお店を作っていますが、マニュアルもしっかりしていますし、必要項目を埋めていくだけでショップが開設できるんです。
WEBの知識があった方がいいのは、元々の機能よりも少し自由なことをしたい場合。
思った通りのレイアウトやデザインにしたいとき、少々の知識があると強いですよ。
商品を配送するための資材

ネットショップは商品を購入していただけたら、お客様に配送します。
そのため、発送用の資材は必須。
発送用の箱か袋
商品によって、箱で送るのか袋で送るのかを予め決めておく方がスムーズ。
適したサイズの入れ物はある程度ストックがあるほうが便利です。
緩衝材
商品を衝撃から守ってくれる緩衝材も、配送用の入れ物と併せて絶対にあった方がいいアイテム。
緩衝材と一言で言っても、プチプチもあればミラマットのようなシートタイプのものもありますし、紙パッキンにボーガスペーパーなどなど、意外と選択の幅はあるものです。
私は紙パッキンを使っていますが、開封時にお客様が箱を開けて商品を見るとき、気持ちが華やぐと思って選びました。
ただ、万能ではなくて、紙パッキンて、切れ端がポロポロと床に落ちたりして片付けの手間があったりするんですよね。
紙パッキンよりいいと思う緩衝材に出会ったら切り替えようかと思っています。
商品を個包装するための透明袋
細かな商品を扱っているなら、小分けの袋もあった方がいいと思っています。
透明な袋に商品を入れてから外箱に入れた方が衛生的にも見栄え的にもよくなります。
アクセサリーならば台紙
私のメイン商材はアクセサリーですので、お店のロゴ入りの台紙を用意しています。
おもむろに袋に入っているだけよりも、台紙にセットされているほうが高級感がありますよね。
その他ないと困るもの
そのほかにもないと発送できずに困るものというものがいくつかあります。
プリンター
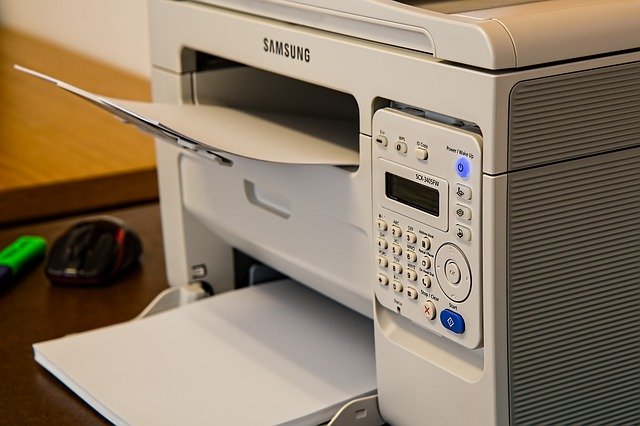
ネットショップは商品の発送時、納品書を同封します。
BASEでは納品書をプラットフォームが作成してくれて、ショップオーナーはプリントアウトするだけでいいので楽々なのですが、プリンターがなかったらコンビニでのデジタルプリントサービスを使用するなどしなくてはならないので手間が増えてしまいます。
ショップカード
必須ではありませんが、お客様に一言メッセージを書き添えたいと思った時、カードがあると便利です。
納品書に書いたり、箱に直書きするという方法もあるかもしれませんが、納品書はお客様がそこに勝手に書き込まれたくないと感じるかもしれません。
カードなら、「ここには書かないでほしかった・・・」とはなりませんので安心です。
実店舗に商品を置くために必要なモノ

ネットショップは必要になるものが主に配送用の備品でした。
ではそれに対して実店舗に商品を置くために必要になる物には何があるのでしょうか。
商品を陳列するための台座や箱
実店舗では、お店の一角に商品を置かせてもらうことになりますが、お店が用意してくれるのは基本的にスペースだけ。
商品をどのようにディスプレイするかなどは自分で考えることが多いようです。
となると、ディスプレイに必要な台座やPOP、下に敷くクロスといったものはすべて自分で用意することになるんです。
商品とマッチする雰囲気のディスプレイ用品を準備しておくのは、前々から準備しておかないと焦ってしまいますので注意が必要です。
商品を際立たせたり季節感を出す飾り
無機質なスペースに商品だけを置くのでは、通りすがりのお客様に目をとめてもらえないかもしれません。
そこで、スペースを季節に沿った色味や素材を使って飾ることもとっても大切な準備なんです。
春は華やかなピンク色や新緑の緑色、夏は海や空を連想させる水色など、季節にも自分の商品にも合う色で商品棚を素敵にカスタマイズするのがおすすめです。
値札
ネットショップと実店舗の大きな違いはこの値段表示かもしれないと私は思っています。
ネットショップはページに値段を表示するので、商品には値札をつける必要がありません。
お店の値札を使わせてもらえるのか、それとも自分で準備する必要があるのか、事前の打ち合わせが必要です。
お店に提出する商品情報
実店舗に商品を置かせてもらう場合の多くは、自分のお店ではなく、他の方のお店に間借りさせていただくことが多いと思います。
その場合、そのお店のスタッフの方に自分の商品の会計をしてもらうことになります。
だから、どの商品をいくつ納品しているのかを表にして提出するなどの情報共有が必要になります。
お客様にショップを知ってもらうための工夫
お店に商品を置かせていただくことができたとしても、そこでゴールではありません。
全然知らないブランドの全然知らない商品を、通りすがりのお客様が突然買ってくれる確率は決して高くないからです。
だから、むしろ商品を置かせてもらうことはスタート。
そこからショップや商品を知ってもらうためにあれこれする人が多いようです。
POPを作ったり、テイクフリーのカードを置いたり。
思い思いの工夫をしましょう。
ネットショップより少々多めの在庫

店舗で置かせていただく商品は、自分でメンテナンスに行かない限り増えません。
だから、アイテムごとに少々多めに置いておくくらいでちょうどいい。
特に主力の商品は、売れてしまっても次のものが出せるように、少し多めに準備が必要です。
ネットショップと同じ透明袋や台紙
陳列している商品によっては、商品を小分け用に透明の袋にいれるのはネットショップと同じですね。
ネットショップと違って、お客様が商品を手にすることができる店舗では、商品を汚れや痛みから守ったりするために準備をしておきましょう。
今回反省したこと
実店舗の商品陳列の準備をしていて、また実際に行ってみて反省して事がいくつかありました。
名刺を作っておくべきだった
何よりもまず、自分の名刺を作っておくべきでした。
会社員の私は、職場の名刺はもちろん持っていますが個人としての名刺はまだ作っていませんでした。
せっかく商品を置いてくれるというお店の社長さんにお会いするのに、私は名刺を渡すことができない。
これは結構恥ずかしいものです・・・。
在庫を抱えていなかったので、作品作りが大急ぎになった
そしてもう一つ反省したこと。
それは、商品点数が足りなかったということ。
ネットショップは一つ売れたらまた一つという感じで、自分のペースで製作ができますが、実店舗となるとそうはいきません。お店が「このくらい」と言った分くらいは在庫できるようにしておかないと信頼を獲得できません。
今後はもう少し多めに在庫するようにしていこうと思いました。
ここから更に頑張ってPas Malを盛り上げていきます

このように、学びの多い実店舗チャレンジとなりました。
結果、2店舗にPas Malの商品を置かせてもらえることになり、これからますます頑張ろうと思っているところです。
何事も同じですが、自分で動いてみて初めて分かることってありますよね。
今回はまさにそんな感じで、本当にチャレンジして見て良かったなと思いました。
これから実際に商品を置かせてもらったらまたどんどん記事にしていきたいと思っています。